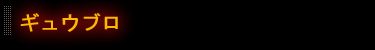
庸夫は馬喰では無い。小さくとも精肉店の息子である。
まずは自店の商品集荷のために農家を回り始める。また、家畜市場にも出入りする事も憶えた。
農家の人々は温かく彼を迎えた。正規に店を構える、信頼できる家のお兄ちゃんは他の馬喰達よりも頼りに出来たからである。農家も家畜が換金されると、季節外の臨時収入を得られ本当に助かった。地方に必要な仕事であったのだ。
「どうせ頼むなら馬喰達よりも庸夫ちゃんの方が信頼できる」こうして徐々に農家生産者との繋がりを拡大出来つつあった。
庸夫は愛車「陸王」で信州各地を走り回った。
当時は農協系のチクレンも経済連も組織化が遅れ、地元に大きな勢力が存在しなかったことも幸いし、大きな追い風を彼は感じながら、拡大に夢中に成って行く。
いつの時代も市場は情報の市場でもある。家畜市場での話題といえば、地元で集めた牛達と同じ物が都会の市場では信じられない高値取引をされているらしい…
「俺にもできるだろうか」「一山当てて家族にもっと楽をさせてあげたい」
家畜市場に集まる馬喰たちは、全国各地を渡り歩いている強者も多い。庸夫は都会の市場規模を彼等から知り、彼等から出荷方法も同時に学んだ。年少だったのが幸いし、可愛がられてもいたのだ。
しかし、実現には能力資力も全く足らず、地元各地を回り続ける日々を送っていたが、少年から青年へと成長するとともに、野心が芽生え渦巻く庸夫であった。
当時の精肉業は畜産業と同義である。
電話一本で成型肉が届く筈もない。まずは家畜を集めることが最も重要な業務であった。今では死語となった馬喰が家畜の流通を担って、時代の風を受けて活躍していた時代。
馬喰達は現在で言う相場師である。ギャンブラーでもあった。
彼等は扱う品は牛でなくとも良い、米でも小豆でも不動産でも良かったはずである。換金性の高い商品としての家畜に興味はあっても、精肉して流通させ、「旨い栄養のある肉を庶民にも食べさせる」ことにより国家国民の栄養状態を向上させ、日本人の健康増進に寄与する。と言った政府の国策には興味を持たなかったはずである。
当時の食肉流通。全国に馬喰のネットワークはあったが、戦中戦後の大混乱の時勢。人が食べていくのに精一杯なのに牧場経営なんて成立するわけがない。農耕用の牛や馬が彼等の手により流通していたに過ぎない。
しかし。利ざやが稼げる馬喰稼業は業界の規範や市場の公平性が整備されていなかったので、大きな利益を生んでいた。
戦後のGHQ占領時代、彼等の求めに応じて牛肉を集荷できる精肉業の老舗達は、ドル決済にて巨額の富を得ることが出来た。その手先としての馬喰達も大活躍できた時代だ。
現在の東京の食肉に関わる大手企業はその末裔たちである。
時代の追い風を受けた老舗精肉店は、東京、名古屋、大阪など都市部各地で成長発展、企業化し始めていた。
集荷も自社社員と新設食肉市場で調達できるように成っていた。
そして、馬喰達は食肉流通の整備と商取引の近代化とともに役割を失い、衰退の一途をたどる。彼等は家畜取引は出来ても、精肉技術や設備すら持たない。
利ざや稼ぎが無くなれば、辞めるだけの零細業種となっていった。
中には時代を見据え、近代的な食肉工場を経営し成功する者も現れたが、少数派であった。多くの馬喰達は時代の潮目を読み間違え、この業界から去っていく。
当時の日本の食肉事情は、明治維新により天皇の勅旨として肉食を解禁、政府が奨励し年月を経てはいたものの、組織的な畜産業はまだ発展途上であった。
明治時代全般に置いても、洋食屋卸の精肉店と外食としてのすき焼牛鍋屋は新しい物好きの男性を顧客として繁盛していたが、肉は食べない人々、台所に持ち込ませない女性たちも大勢存在した。肉料理といえば、現在のバーベキューのように庭先で男達がすき焼や牛鍋を調理し食卓で食す…何だか現在では笑える光景が日常があった程だ。
生産も流通も消費も明治大正の黎明期から、戦中戦後の空白の食糧事情の哀しい時代を経て、日本は昭和の高度成長を迎えつつあった。
都会では消費意欲に満ちた人々が畜肉を求め、牛肉だけでなく養鶏養豚事業も各地で初まり、飛躍的な肉類消費量が増えていったが、地元信州はまだまだ田舎で前近代のまま、「牛肉なんて旨くでもない、乳臭いだけだ」などと言われ、生産地なのに消費は振るわなかった。
しかし、地元が温泉歓楽街であったり、志賀高原がスキー場として大開発の時期を迎えつつある時期を迎えていたこともあり、都会の人々が沢山訪れ、肉類の消費は大きな伸びを見せていた。
庸夫の家の店の経営状態も、従来の地元旅館業に加え新しく開発された洋食を提供するホテル。そして志賀高原スキー場の大ブームの訪れにより、大きな成長を見せていた。
いよいよ、時代は仕入れが最重要な課題となってきた。生体家畜を取り扱えない精肉店も、人口の多い街に増え始め、地元以外からも注文が来るようになる。
農家を回るのも交通手段が小型バイクでは遠征できず、商談と移動の機動力に劣る。庸夫は思い切って当時のスーパーバイク「陸王」を購入した。派手で目立ったが、遊び半分ではなく必需品となる。すでに、庸夫は農家に肥育の相談にも乗るようになっていたし、自分は商談と決済に専念し、運搬は馬喰達に任せる。分業制となりつつあった。
支店配属、これがどうもいけなかった。初めて実家以外の場所…母や兄たちの目を逃れてパチンコにのめり込んでしまう。本来ギャンブルは好まなかったが、なにしろ暇が有り過ぎた。人生の目的らしいものも、どこにも見当たらない…
まだ、自分の将来を決めかねていた庸夫には悶々とした辛い日々だった。
「俺は食べるのが大好きだし、洋食の板前でも目指そうか…」とぼんやり考えている少年時代、まだ畜産そのものには興味を持ってない庸夫であった。
精肉店では現在のように牛豚の骨などは不足することもなく、家族、従業員の賄いのご馳走といえば、豚骨スープ!
母は料理上手で店の余り物で子ども達の腹を満たした。庸夫にとっスープ料理は特別な思い入れがある。濃厚なダシに自家製のウドンや中華麺、焼豚こそ入っていなかつたけど、骨までしゃぶり尽くしたものだ。
食いしん坊庸夫の味覚の原点は、こうして母の作る豚骨うどんラーメンから始まる。「洋食の板前」に漠然と憧れていたのも、そこにしか好きなものが無いような気がしていたからだ。
そして渋温泉での月日も経ち、件の「金倉の牛事件」があった。本人の勘違い、大人達の噂話、茶飲み話みたいなものだったかもしれない…
しかし、家業が皇族にも認められる、社会にとって有益な職業だと、勝手に思い込んだ少年の、その後の彼の人生の指標となる大きな出来事であった。
庸夫は心底驚いた。
うちの店が地元ホテルに納品した牛ロースが、皇族の尊い方から高評価を得て、お詞を賜った…。
「俺が地元金倉の農家からあげてきた牛だ…」
信じられない出来事だった。
当時、皇族と接点が有るということは庶民の日常ではあり得ず、少年庸夫にとっては晴天の霹靂。
「俺はこれだと思った」その時初めて家業の存在価値を悟った。
「俺の仕事」が初めて社会から高い評価を得た瞬間だった。
実社会との接点。モヤモヤ鬱々とした日常からの脱却。
これを機会に庸夫は畜産業に励み、夢中に成って行く。庸夫が十代後半のことである。
庸夫の家は畜産業と精肉店を父の代から生業としていた。しかし、父は病を得、若くして逝去。
母と兄二人弟二人妹二人が残された。
すでに兄二人は母を助け商売に励み、店は職人たちと共に大所帯。拠点となる信州湯田中温泉は、娯楽を求める戦後の信州において隆盛の道を登りつつあった。
中学校を卒業し、必然家業を手伝うことに成る庸夫。
しかし、十代の少年には面白くも可笑しくも無い。母は忙しすぎるし、兄達は居るし、職人達は奪い合って仕事をしてるし…なかなか、自分の居場所を見つけられない日々。
とりあえず、ということで、隣町の渋温泉の支店販売所に配属となった。
はじめに…
この物語は、義父庸夫の晩年十五年間の会話を元に、忠実に書いたつもりです。
しかし、元々文書化するつもりなど無かったので、メモなどは一切取っておらず、年代考察の前後不確実、人間関係、私の知りえない真実との不合致などが含まれていると思われます。
親族及び当時の関係者の方々「それは違う」と訂正をお求めにならないようにお願い致します。この読物はあくまで、「ものがたり」としてお読みください。
こういう私小説みたいなものは、私はプロではないので傷つく人が生じてしまうのは頂けません。出来る限り配慮はしたつもりですが、故人やご親族、関係者の方々にに無礼な箇所がありましたら、お許し下さい。先に慎んでお詫び申しあげます。
義父庸夫は筆不精でした。
私の祖父本治郎筆の書額を褒め称え、珍しく羨望の眼差を見せていました。
きっと、「私達や孫の世代に伝えたい」と思っていた畜産人生の話があったと思います。
先日、甥泰匡と食事をしていた際、彼が祖父の若い頃の事を何も知らないことに驚きました。
あれほど君のことを、愛してやまなかった庸夫の遺志を、不肖私が代筆させて頂く所存です。
今のところ、完結しそうもありません…
庸夫が愛してやまなかった、泰匡君に捧ぐ。


